まず押さえるべき「すごい回復」基本のキーワード
まず押さえるべきは、「疲労は脳からの警告サイン」という考え方。
単なる“だるさ”ではなく、過労やストレスが積み重なった結果、脳が「これ以上は危険」と発しているのです。
「疲れは我慢するものではなく、正しく回復させるもの」とまずは認識。
そのうえで自律神経、血行、腎臓、炎症などへの正しい対応方法を教えてくれます。
アップデートしたい「食べ方」のスゴ技
多くの健康本が「食事は疲労回復の基本」と説いています。
- 抗疲労成分:イミダペプチド(鶏むね肉・サラダチキンなど)、クエン酸
- 食べ方の工夫:血糖値を急上昇させない、よく噛んで食べる、食べる「時間」も工夫する
- 腸内環境:乳酸菌や食物繊維を摂取し、腸から元気をつくる
上記の内容はすでに世の中に広く浸透していますが、私が心に残ったのは、“食べ方の作法は年齢とともに変わる” の箇所でした。
60歳からは、「野菜ファースト」から「肉・魚ファースト」に切りかえたほうがよい。と記述がありました。
良い効果があると思って同じことをずっと続けるのではない。
これは良いことなんだ。とバイアスにかかるのではなく、臨機応変に変えていくことは、ビジネスのみならず食事でも重要です。
小さなコツほど覚えたい!「間食・お酒」のスゴ技
疲労回復の観点から見ると、間食は「敵」ではなく「使い方次第で味方」になります。
ミックスナッツや果物、ヨーグルトは血糖値の安定に寄与し、集中力を保ちます。
一方で、砂糖たっぷりのお菓子や清涼飲料水は急激な血糖値変動を招き、逆に疲れを悪化させます。
また、お酒については最近の研究では、まったく飲まない人のほうが、少しだけ飲む人よりも死亡リスクが低いという研究もあるようです。
多量の摂取については言うまでもなく、「疲れを癒すどころか、肝臓に負担をかけ、睡眠の質を下げる」と指摘されています。
晩酌で深酒してしまうことで“気持ちの疲れ”をリセットできた気になるものの、実際には体を蝕む結果になりかねません。
リフレッシュ度120%の「疲れない睡眠・お風呂」
睡眠は、「質」×「時間」が大事。
これは多くのベストセラー健康本に共通する結論です。本書では具体的に、
- 40℃前後のぬるめのお湯で10~15分入浴
- 就寝前はスマホ・PCを避け、光刺激を減らす
- 寝室環境を整え、脳は涼しく、体は温かく
など、科学的に裏付けられた多くの方法を紹介。
特に「お風呂」は体温調整とリラックス効果で睡眠の質を劇的に改善します。
多くの健康本が推奨する“入浴法のエッセンス”を、本章で効果的に学べるのが魅力です。
やせたい人ほど陥りやすい「運動・ダイエット」の勘違い
「ダイエットは自分に甘いほうが成功する」――。
ダイエットはストイックなものだと考えていた私は驚きましたが、本書では「ダイエット=善とは限らない」という説を教えてくれます。
そして「ダイエット=やせること」ではなく、健康的な体をつくる体重調節法であると書かれています。
また、運動習慣がない人がいきなり強度の高い運動をするのは危険で、会話が続けられる程度の不可で、ウォーミングアップを行う必要があります。
適切な運動による血流改善により、疲労物質が分解され、自律神経のバランスも整います。
体重だけにとらわれて無理な食事制限や激しすぎる運動をするよりも、継続的な運動で“疲れにくい体”を作ることが推奨されています。
100冊分の知見が裏打ちするのは「やりすぎない運動こそが疲労回復の鍵」という実践的メッセージです。
まとめ
本書の最大の価値は、膨大な健康本から「信頼できる部分だけ」を抽出していることです。
世の中には健康法があふれていますが、玉石混交でどれを信じればいいのか迷うのが現実。
この本を読めば、栄養・間食・お酒・睡眠・お風呂・運動といった日常の基本習慣について、「何が正しく、何を避けるべきか」が明確にわかります。
年齢を問わず、学生から働き盛りの世代、そしてシニア層まで、誰もが「疲労」と無縁ではありません。
むしろライフステージごとに疲れの質は変化し、その都度適切な回復法を知っているかどうかが、心身の健康を大きく左右します。
人生100年時代を健やかに生き抜くために、この本は知識のショートカットとして役立ちます。
100冊分の情報量 × 医学的エビデンス × 実践的ノウハウ
この三拍子がそろった『すごい回復』は、まさに「全世代に向けた、疲れと向き合うための指南書」と言える一冊でしょう。
そして、無理のない範囲で行動に移すことが、最も大事だと学びました。
 WAKA
WAKA知識を身につけ、できることから
無理のない行動を!


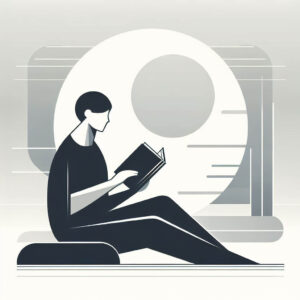

コメント